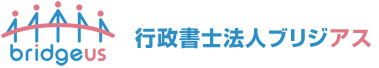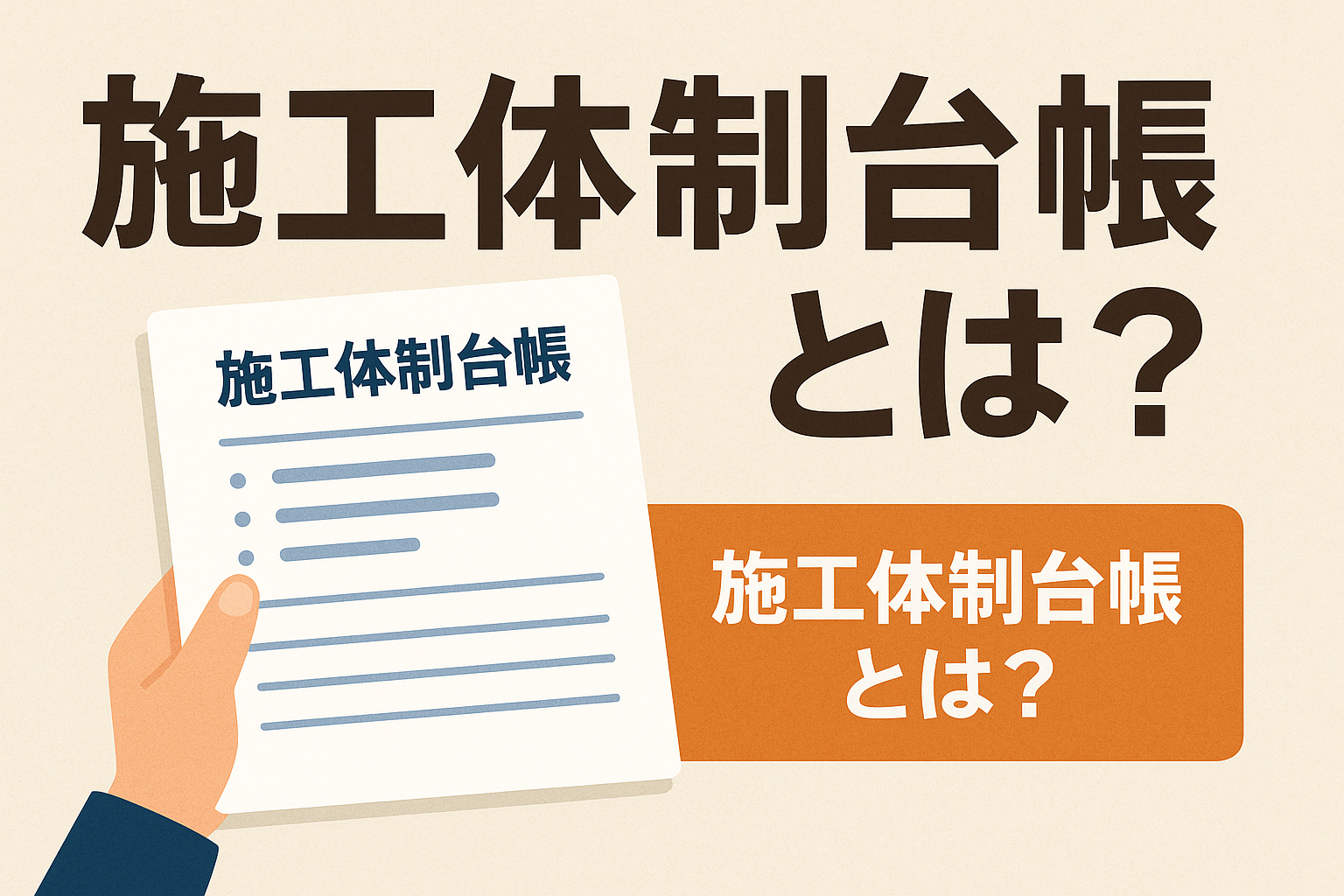スタッフ笹森です。
今回は、建設工事の適正な施工を確保する上で非常に重要な「施工体制台帳」について、特にその作成義務と備え付けのルールについて解説いたします。
「施工体制台帳」とは?
施工体制台帳は、元請業者が工事全体の施工体制を的確に把握し、工事を適正に進めるために作成する書類です。建設業法という法律で定められた、重要な義務の一つです。
作成義務が発生するケース
「うちの工事では必要なの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
作成義務が発生するのは、次のケースです。
- 元請の特定建設業者が、下請契約の合計金額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる工事を行う場合。
※ただし、資材の納入、調査業務、運搬業務、警備業務などの契約金額は、この合計額には含まれません。 - 公共工事を受注した場合。この場合は、下請契約の金額にかかわらず、施工体制台帳の作成が必要です。
このルールは、公共工事・民間工事のどちらにも適用されます。
施工体制台帳はどこに備え付ける?
作成した施工体制台帳は、工事が完了し、発注者に目的物を引き渡すまでの間、工事現場ごとに備え付けることが法律で義務付けられています。会社の事務所での保管ではない点にご注意ください。
また、工事完了後も、一部を抜粋したものを5年間保存する義務があります。
- 建設業法および関係法令により、工事の目的物を発注者に引き渡すまでの間、現場で施工体制台帳をいつでも閲覧できる状態で保管すること。
- 公共工事の場合は、作成した施工体制台帳の写しを発注者(監督員)へ提出した上で、現場にも備え置くこと。
※ただし、CCUS(建設キャリアアップシステム)などで発注者が直接内容を確認できる場合は、提出が免除されます。 - 民間工事の場合も、該当工事で施工体制台帳の作成義務が生じれば同様です。発注者から閲覧請求があった際には、現場での台帳を閲覧に供すること。
工事完了後は、「担当営業所」で保存します。保存期間(通常5年間、住宅の新築工事は10年間)は、必要時にすぐ取り出せるよう、分かりやすく管理できる場所に保管しましょう。
「施工体系図」との違いも知っておこう
施工体制台帳とよく似た書類に「施工体系図」があります。こちらは、各下請負人の担当工事内容が一目でわかるようにした図のことです。
施工体制台帳が「現場での備え付け」であるのに対し、施工体系図は工事期間中の「掲示」が義務付けられています。
- 公共工事: 工事関係者が見やすい場所と、一般の方(公衆)が見やすい場所の両方に掲示します。
- 民間工事: 工事関係者が見やすい場所に掲示します。
まとめ
施工体制台帳の作成と現場への備え付けは、建設業法や入札契約適正化法で定められた、特定建設業者の重要な責務です。適正な工事施工とコンプライアンス遵守のために、ルールを正しく理解し、実践していきましょう。
神奈川県横浜市の行政書士法人ブリジアスは、建設業に特化した行政書士法人です。
建設業許可に関するお困りごと等がございましたら、お気軽にご相談ください。